こんにちは、のちこです。
今日は、最近読んだ本の感想を書きたいと思います。タイトルは「世界一やさしい内向型の教科書『静かな人』の悩みがちな気質を直さず活かす3ステップ」です。
「大人数の場が苦手」「すぐに返事ができない」「一人反省会が止まらない」――こんな悩み、ありませんか?
もしかしたら、それは性格の問題ではなく、あなたが「内向型」だからかもしれません。そして、それは決して直すべき「欠点」ではない、とこの本書で説明されています。
こちらの書籍の著者は、ご自身が内向型ゆえの生きづらさに悩んだ経験をもとに、現在はカウンセラーとして活躍されている方です。内向型にありがちな性質あるあるや、その性質をどうプラスに変換するか、などが丁寧に記載されています。
特に本書では、その特性を「認識・理解」するところから、「活かす」ためにどう考えるのか、という部分にフォーカスが当てられています。
内向型であることを認識し、その先どうしたらいいのか、と悩んでいる方にもおすすめです。
私自身、「そうなの!そうなの!」と思いながら読み進めました。
きっと生き方のヒントになる部分がたくさんあると思います。
外向型が「正しい」という空気の中で
私たちは、小さい頃から、外向型の人たちが「正しい」という空気感の中で生きてきたと思っています。
大人しいとか、声が小さいとか。そういった性質は、「悪い」と言われることはないけれど、なんとなく「よくないんだろうな」という同調圧力にさらされてきたように感じます。
そんな風に、小さい頃から「外向型がよし」とされる世界で、なんとなく居心地悪く感じたことのある方であれば、きっとこの本を読むと心が楽になると思います。では、私が特に共感した部分をご紹介しますね。
内向型の人が抱えがちな5つの悩み
1. 質問にすぐ答えられない
この理由として、本書では「一旦質問を理解して、回答を整理してリハーサルを経てやっと声に出す」というプロセスが紹介されていました。
確かに言われてみれば、脳内でリハーサル、しています。(むしろ、みんなすると思っていた!)
そうそう、私は質問の意図を理解することに時間をかけてしまうので、返事に少し間が空いてしまうのです。1対1だと、「急いでなにか言わなきゃ」と焦ってしまうし、数人の前だと、変に沈黙した空間ができて余計に焦ってしまいます。
これ、私の頭の回転が鈍いからだと思っていたのですが、内向型の特徴だそうです。そうと思うと、必要以上に自分を責めずに済みますよね。
自分の処理スピードが遅いのではなく、丁寧に考えているだけなんだと思うと、幾分気が楽になった気がします。
2. 大人数の場に行くと疲れる
これも当てはまります。実は先日、職場の人に誘われて、交流会のようなものに参加してきました。これが、ただの交流会ではなく、ちょっとした運動会も兼ねていたのです。
自己改革中ですし、これを機に自分の殻を破れるかも?なんて思って参加しましたが、甘かったです。
やはり私には厳しかった。
運動会が始まるまでの時間、種目決めの時間、準備体操の時間。すべて逃げ出したい気持ちでいっぱいでした。
その最中も「やっぱり来るんじゃなかった」という思いと同時に、「やっぱり私って社会人失格なのかも」「大人として終わってる」――そういう思いが頭の中をぐるぐるしていました。
私は「克服すべきこと」「社会人として必要なコミュニケーション能力」と捉えていました。でも、この本を読んで、自分が持つ性質だと思って割り切った方がいいのかも、と思えるようになったのです。
ただ、一つだけ。運動会の最中に知らない人に自分から話しかけたことだけは、ほめたいと思います。笑
3. 予定外のことが起きると余裕がなくなる
これも当てはまります。
とある職場を受けた時、採用担当の方が、昔私と働いたことのある方と顔見知りで、その方に連絡をしたそうです。「受付で考えてるけど、どうだろうか」という問いに対して、昔一緒に働いた方は「難しいかも」と答えたのだそう。
私自身、受付は無理なのでありがたかったのですが、後日その理由を聞いてみると「やっぱりあれこれ忙しいかなと思って」と濁された回答でした。(そりゃそうか。笑)
受付なんて、予定外のことばかりでしょうから、私のその性質(余裕がなくなってしまう)を見抜いてのことだったのだと思います。正直、この話を聞いた時、「仕事ができない」と言われたような気がして、少し認めるのが嫌でした。でもこの書籍のおかげで、今改めて受け止めることができた気がします。
4. 同時に複数のことを進めるのが苦手
これも当てはまります。
せっかちなところがあるので、色々なことを同時に進めてしまうのですが、結果どれもうまくいかない、ということがしばしばありました。例えば、2つの関連性のない資格試験の勉強を同時進行で進めるとか。
35年たってやっと、一つのことに集中しないと無理なタイプであることを自覚しました。
5. 「一人反省会」が止まらない
これも当てはまります。でもこれに関しては、最近は少し克服しつつあるのです。
というのも、X(旧Twitter)で、「自分の言動をどう解釈するかは相手に任すべきこと」といったようなポストを見たのです。これまでの経験を踏まえると、確かにと思う部分がありました。
自分のことをわかってくれている人は、真意を汲んでくれます。さほど親しくない人は、正直どう受け止められたかは分からないけれど、私が気にすることではない、と思えるようになりました。
それでも一人反省会が始まってしまったら、「でもま、いっか」と思うようにしています。完璧じゃなくていいんだという開き直りも、大切なのかもしれません。
友達作りやコミュニケーションの悩み
この章は、読んでいて本当に慰められました。笑
「暗い性格だと思われたくない」と思ってその場を取り繕ってしまう。これ、特に小中学生の頃はめちゃくちゃ思っていました。複数人で話しているときも、「あ、反応悪いな」「なんかずれた話しちゃったかな」と頭の中が忙しかったのも、確かにありました。
無理して「明るいキャラ」を演じた過去
ここで昔話なのですが、中学生の頃、おとなしく見られるのが嫌で、性格を変えたいと思っていた時期がありました。
自分がどんなふるまいをしていたのかは覚えていないのですが、一つだけ覚えていることがあります。「のちこって、無理してテンション上げてるのが分かるから、ちょっと痛いよね」という陰口です。
当時の友達が教えてくれました。(ちなみにこの子は悪くないんです。当時の私は、悪口さえも把握しておきたかったから逆に助かった)
我ながら無理してたのでしょうねぇ…。ちなみに、「新しい私」は結局続きませんでした。無理して作った自分は、やっぱり長続きしないんですよね。
内向型=静かな人?実は違います
内向型に関する本のタイトルは、「内向型」と「静かな人」がセットになっているものが多いようです。そのため、内向型=静かな人というイメージがありますが、必ずしもそうではない、と筆者の方はおっしゃっています。
筆者曰く、内向型の人は、「静かな人」ではなく「静かな時間が必要な人」だそう。
これを聞いてどう思われますか?
私は、とても腑に落ちました。
というのも、私も初対面こそは大人しいのですが、友人といるときはそれなりに話します。むしろ話し過ぎたかなと思うときもあるほどです。
内向型なのに、親しい友人とはものすごく話しまくる自分。矛盾を感じて、気持ち悪ささえ感じていましたが、この書籍を読んでホッとしました。人と話すのが嫌いなのではなく、エネルギーを回復するために一人の時間が必要なだけなんですね。
「外向型に変わりたい」と思ったら
こちらの著書では、「内向型を活かそう」という趣旨が記載されていますが、それでも外向型になりたい、という場合は、エッセンスとして取り入れることを推奨されています。
この方法が、自分を苦しめることなく自分を好きになる秘訣だそうです。
以前の記事で書いたAさん(こちら)は、おそらく、あの社交性からして外向型の方だと思います。私がAさんを目指して行動をコピーするのは、やはりどう考えても無理がある。Aさんの素敵な部分だけを取り入れる方が私にはいいみたいです。
完全に真似するのではなく、自分に合った部分だけを取り入れる。これなら無理なく続けられそうですよね。
この本に詰まっている有益な情報
本書には、他にもたくさんの実践的なアドバイスが載っています。
ネガティブになった時の対処法・インプットばかりの対処法
ネガティブになった時の対処法を準備しておく、といったことや、学ぶばかりで行動に移さないことへの対処法なども紹介されています。
ちなみに私も学ぶばかりで行動に移せないタイプなのですが、まず、学び始める前に、学ぶ目的・学びを活かすために次に何をするかを自問することをおすすめされています。確かに、これをやるだけでだいぶ変わりそうだと思いました。
良かったことを書く習慣
ノートにその日あった良かったことを書く習慣をつけると、ここから自分の傾向をつかむことができるそうです。予想できるストレスに対して事前準備ができるので、ぜひ実施したい習慣ですね。
自己理解を深めるワーク
その他にも、認知の歪みについてや、ネガティブ思考とほどよい距離をとるワーク、価値観を導くワークなど、自分を理解するためのワークも記載されています。
自分の強みをどうやって見つけるか、そしてその強みを活かすまでのフローも丁寧に紹介されています。読むだけでなく、実践できる内容がたくさん詰まっています。
私の心に響いたメッセージ
本書の中で特に心に響いたメッセージがこちらです。
- ないものねだりではなく、持っているものを活かして自分らしさを発揮しよう
- 周りからの目線を気にするのではなく、「自分がどうしたいか」を大切に
- 「苦手なことを克服したい」という気持ちを手放すこと
3つ目に関しては、まさに、慣れない運動会に参加して落ち込んだ私に向けてのメッセージかと思いました。笑
苦手なことを無理に克服しようとするのではなく、得意なことを伸ばす。外向型になろうとするのではなく、内向型の強みを活かす。そんな発想の転換が、楽に生きるコツなのかもしれません。
今でも思い出す苦い思い出
大学に入りたての頃、クラスでの懇親会がありました。その時、テーブルでゲームが始まったのですが、そういう「ワイワイしたノリ」が苦手な私は「私はいいや」と言って見ていたのです。
その日の夜、当時流行っていたmixiのクラスコミュニティに、私と思われる悪口が書かれていました。あだ名にはなっていましたが、私の苗字をもじっているのは明白。そこには「あの人結構KYかも」と書かれていました。
書いたのはゲームの時隣にいた男の子。私のことだとすぐにわかりました。
その子、ゲームが終わった後、あからさまに私への態度が変わっていましたから。笑
そのコミュニティは、友達が教えてくれたのでひっそり見ていたのですが、その男の子たちは私が見ているとは知らなかったみたいです。次の日、このことを友達に話しながら泣いてしまったのを覚えています。(その後すぐ、参加者以外は見えないようになっていました。)
このエピソードは、私の頑固さもあっての出来事なので(したくないことはしない。笑)特殊かもしれません。でも、悲しかったこと、自分ってやっぱりおかしいのかなと思ったことは事実。
当時の自分がこの本を読んでいたら、もしかしたら違っていたのかもしれません。
まとめ:内向型は「直すべきもの」ではない
内向型であることは、決して欠点ではありません。むしろ、深く考える力、一つのことに集中できる力、相手の気持ちを察する力など、素晴らしい強みがたくさんあります。
外向型になろうと無理をするのではなく、内向型の自分を受け入れて、その特性を活かす。それが、自分らしく楽に生きる秘訣なんだと思います。
この本を読んで、私が一番感じたのは「自分を否定しなくていいんだ」ということでした。
実は本を読んでいる最中も「これは違うかも?」と無意識に内向型の特徴を否定しようとしている自分がいました。思っている以上に自分を否定してしまっているのかもしれません。
(その後、今までの経験を考えたら当てはまっていることに気が付きました。笑)
それに、これまで色々な本を読んだりして、「ないものねだり」からは卒業できたと思っていましたが、まだまだ卒業できていない自分を発見することもできました。
実は私自身、趣味で心理学を勉強していた時期があるので、内向型であることは自覚していました。ただ、治せるものではない、単なる特徴、とも認識していたので、「活かそう」という発想には至らなかったのです。もう少し早く、この本を読んでいればよかったと思います。
内向型で生きづらさを感じている方、大人数が苦手で悩んでいる方には、ぜひおすすめしたい本です。
こちらで「はじめに」が公開されていますのでご興味があればぜひ。
『世界一やさしい内向型の教科書』刊行記念!はじめに全文公開
きっと、読み終わった後には、少し心が軽くなっていると思います。
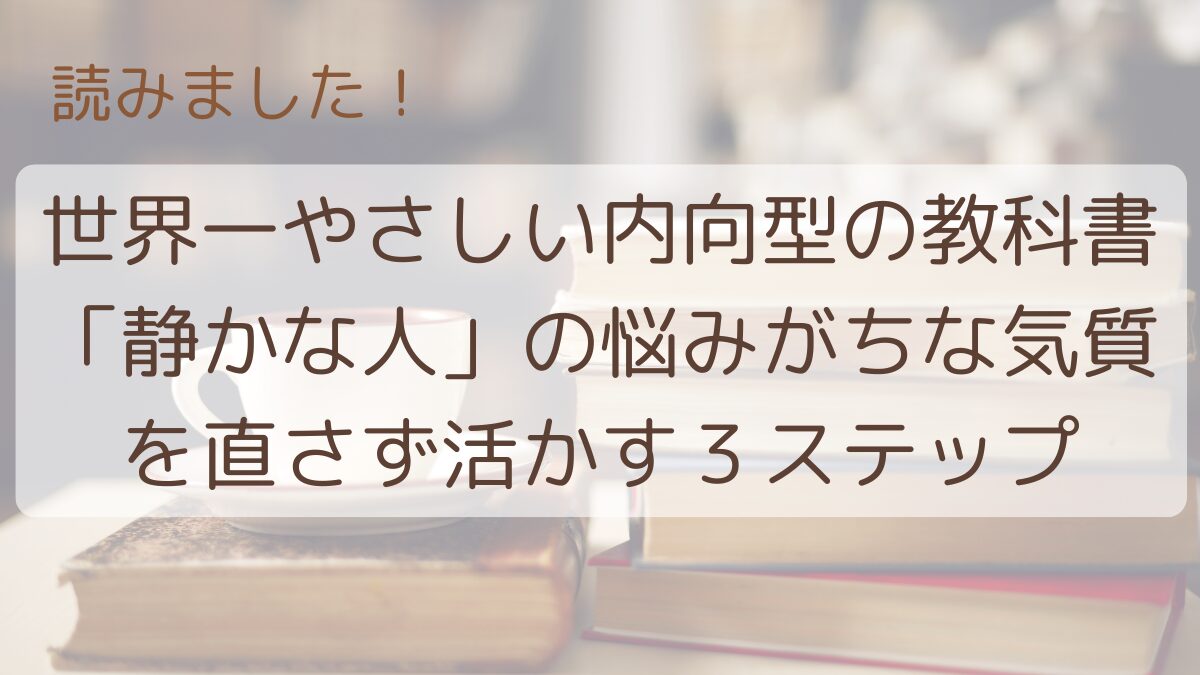
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4698f0f6.1a7c4096.4698f0f7.f5e3c1f6/?me_id=1213310&item_id=21228928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6007%2F9784418246007_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


